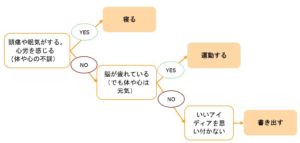こんにちは!ラクです。
なんか露骨に「話したくない」って雰囲気を醸し出してるなぁ…
…そんな風に部下に対して思ったこと、ありますでしょうか?w


仕事へのイラ立ちなのか、上司に対しての反抗心なのか…
そんな雰囲気の時にあなたが自分の話を聞いて欲しいと思って話せば話すほど、
相手はシラ~っとするもの…
今回は、そういった場合の「話の切り出し方」をご紹介!
●プロフェッショナルな一言
●正直に話す一言
●人生を感じさせる一言
さっそく行きましょう!
実は面倒見の良い一言
もう何よりも「働く」ということをイヤに思ってしまっている部下。
そしてその雰囲気が露になってしまっている人。
そういうときにかけてみたい言葉は…こちら!
あなたは、どうなっていたらいいと思うの?


「じゃあもう勝手にしろよ!」と突き放すのではなく、「あなたは本当はどうしたいの?」と、踏み込んで聞いているところに、温かさを感じることが出来ます。
プロフェッショナルな一言
プライドの高い部下だったり、負けず嫌いな部下だったり。こういう部下の場合は実は一度失敗しないと分かりません。
しかし、あまりにも変な方向に失敗されると会社への損害になってしまいます。それを避けたいときにかけるべき一言!
それはいい考えだね。じゃあ例えばxxxのときはどうしようか?


「いいから言うこと聞けよ!」と押し付けず、まずは部下のコメントを受け入れた後で、他の考えも促す…
そうすることで、「上司の指摘の鋭さ」を素直に受け入れることができます。
正直に話す一言
よく失敗する部下…あるいは注意しても全然言うことを聞かない部下。
自分の価値観や経験に固執しているとも言えます。年上の部下にもいるかもですね。
あなたはxxxがうまい。でも●●●の点は、もっと伸ばす必要がある。


部下にとっては若干ズキっと来るかも知れません。しかし、時には正直に伝えてあげる方が、「あ、この上司は分かってくれてるな」と思ってくれるものです。
人生を感じさせる一言
部署異動したばかりだったり、プロジェクトを任せたりで精神的に負担に陥っている部下など…
もしあなたが長年同じ会社に勤めていたり、あるいは似たような経験をこれまでたくさんしてきたのであれば、
多くを語るよりも以下をサラッと伝えるのも、自分の背中を見せられていいかもです!
まぁ…大変かもだけどさ。悪くないよ、こういう仕事も。


上司の重厚さと器が感じられる言葉です。自分の方が知識も経験もあるときには、とても効果的な言葉ですね。
まとめ
このように…大切なのは相手のことを思いやるような一言。
それが必ずしも相手に刺さらなくてもいいんです。
ただ、自分のことを延々と話すより、こちらの方がずっと自分の話を聞いてくれるようになります。
そして…
その一言から会話を発展させていく…
そんなイメージを持ってみてください。