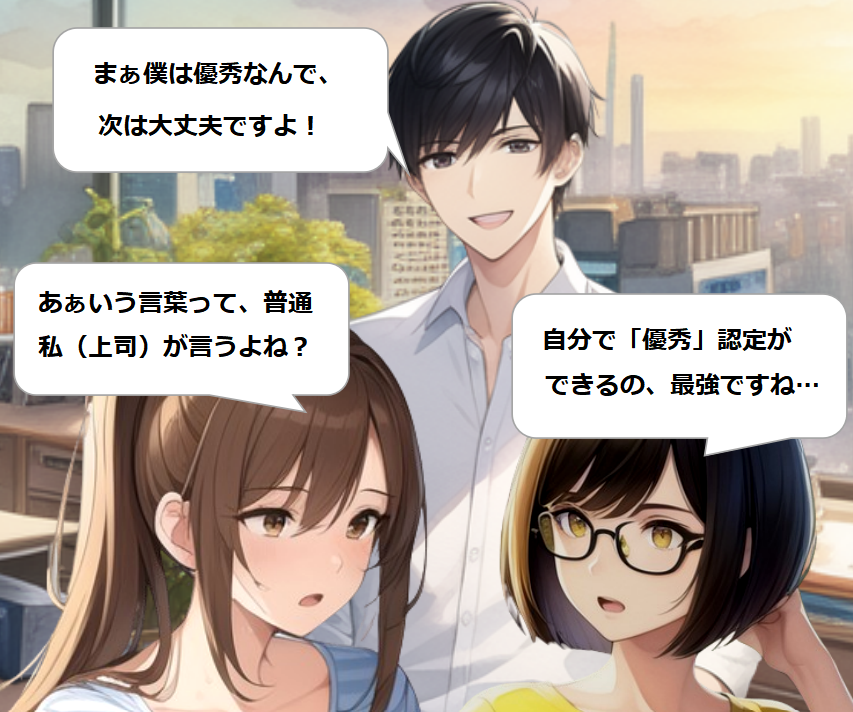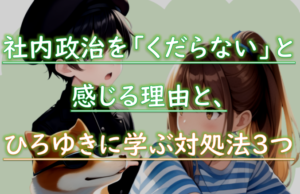こんにちは!ラクです。
「うーーん…あの人は優秀で頭のいい部下なんだけど…
使いこなせないし、なんか扱いにくい…」
…と思うこと、ありませんか?(笑)


本人に優秀だという自覚があるからこそ、上司としては扱いにくいです。
そして、それがゆえに大きな失敗をする可能性もあります。
そんなとき、大切なのは、部下自身の内省を「やんわりと促す」ことです!
優秀な部下だからこそ、内省は大きなメリットを生む可能性があります。
今回のブログでご紹介するカンタンな3ステップを、ぜひ実践してみてください!

実例の紹介
優秀な部下だったが、顧客との会議でメモを一切取っていなかった。
後日会話内容を忘れ、顧客とトラブルに…


他にも以下のような特徴があります。
・教えられても、メモを取らない
・教えてもらっていないと開き直る
・会議で発言しないといけないのに、準備してこない
・何をやっても許されると思っている
・相手を論破しようとする
・周りや上司に確認せず、仕事を進めてしまおうとする
・例外対応に弱い
・自分の価値観を周りに押し付ける
共通点
優秀な部下は、いざとなれば他人より出来ると思っています。
そして、上司にも気に入ってもらえている…と思っている。
これらは「自分は優秀」という自覚がある部下の、利点でもあり欠点でもあります。

その欠点とは、
「何か間違ったことをしてしまった場合、周りは止めにくい」
なぜなら、自分より劣る(と思っている)人たちからのアドバイスは聞きたがりません。
プライドが邪魔するからですね。
そのうち、そのうち大きな失敗をすることになります。

また、もう一つ以下のような欠点があります。
「計画の修正を怖がる傾向がある」
計画通りに行かなかった場合、「最初の計画が誤っていたのだ」と思い込んでしまいます。
そして自分を責め、計画を修正することを恐れます。
そのまま突き進んでしまうと、大きな失敗をすることになります。

内省を促す3ステップ
もう一度先ほどのケーススタディを見てみましょう
優秀な部下だったが、顧客との会議でメモを一切取っていなかった。
後日会話内容を忘れ、顧客とトラブルに…
ここでこんな風に部下に伝えたら、どうなるでしょうか…


そこでご紹介するのが、以下3つのステップ!
① まずは「事実」を本人に認識させる
② 何が原因と思うか本人に聞いてみる
③ 今後どうするか本人に考えてもらう
事実を確認し、原因を考えてもらい、今後についても考えてもらいます。
そしてそれらを、「本人の口から」言わせます。
上司から「ああしろ」「こうしろ」と言うのではありません。
内省の機会を与えるというカンジです。

これは優秀な部下だからこそ取れる手法だとも言えます。
自分で建設的に考えることができて、答えを導き出せるということなので。
(優秀でなければ、「答え」を誰かに求めがちになることもあります。)
対応の具体例
3つのステップを踏まえ、以下のように返してみてはいかがでしょうか?
- 今回は準備もなくメモも取っていなかったですね。結果はどうでしたか?
- メモを取らなかったのは、何か理由があるのでしょうか?
- 次からどうしましょうか?
このように質問をすることで、部下自身に事実を反芻させます。
そして、自分で出した答えに基づいて、アクションを取ることになります。
…もちろん、それでも失敗するかもしれません。
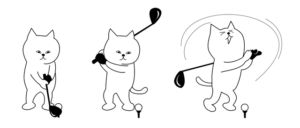
でも、それでいいんです。
「修正はつきもの。大事なのは計画を繰り返すこと」だと、そのうち気付くようになります。
指導の流れ
ザックリとした流れですが、以下のような流れを頭に入れておきましょう。
他人の言うことを聞かず、自分のやりたいようにしかやらない。
自分の考えたいように考え、やりたいようにやってしまいます。
当然、自分の視点しか見えていないので、失敗することになります。
「他人のアドバイスは聞きたくない」ので、自分で原因を考えさせます。
自分で考えさせた後、「ではこれからどうするか」を考えていきます。
それでもまだ失敗するようなら、③に戻って繰り返します。
(でも、決して繰り返すことが悪いということではありません。学びのステップです)

ロールプレイ①
今、トクコさんが部下のマナコさんと話しています。
マナコさんに「新しい役割」をお願いしようとしています!




●細かく指示を出しすぎない。本人の「成長の機会」を奪ってしまうことになる。
●優秀だからと言って自主性に頼りすぎるはNG。必要な指示(線引きなどの決め方)はすること!

ロールプレイ②
どうもマナコさんは、プロジェクトに当たって、会議をうまく進行出来なかった…ようです。




●先ほどと同じく、上司自らが細かく答えを出さない。
●部下自身の話をまず聞いてみて、「じゃあどうしようか」と一緒に考える。
・そのうえで、本人に答えさせる。
心理カウンセラーのおすすめ
部下を知る際に、オススメの方法があります。
それは、以下のポイントです。
それは、「どの程度、物事を広く深く捉えることができるようになっているのか」という意識レベルでの成長段階です。
このことを知るのに、オススメの本があります。
それは「≫なぜ部下とうまくいかないのか(加藤洋平著)」です。
なかなか刺激的なタイトルですよね(笑)
こちらは、カウンセラーに紹介された本です。
そこでは主に以下の3つの意識段階について説明しています。
(厳密には5つ段階があるのですが、以下は主なもの3つをピックアップしています)
自己中心的な認識の枠組みを持つ。他の人の感情や思考を理解するのが難しい
組織や集団に属し、他社に依存する形で意思決定する。会社や上司に従う。
自分の意見を明確に主張するが、自分の価値観に縛られがち。
中長期的な観点から、「自分の部下は、どの段階にいるんだろう」と言うことが分かります。
そうすれば、次のステップに進んでもらうための支援ができます。
例えば以下のような声掛けですね。
「先輩はこう言っていたね。それはどんな背景があるんだろう?」
「あなた自身は、どうすればこの部署にとって良いと思う?」
「一度自分の意見を客観的に見てみよう。主張や論理に弱さはありそうかな?」
「次の部署、君の成長のために〇〇部なんてどうだろう?」

管理職は、自分を知ることが大切

ここまでの話で、あなたの環境が少しでも良くなることを心から祈っています!
しかし…
部下を変えるには、まずは自分を知ることが大切です。
まずは、自分自身に対して以下のような質問を投げかけてみましょう。
ハッとすることも多いのでは無いでしょうか?
●自分は「バイアスが無いというバイアス」に囚われていないか?
●組織に従属しすぎていて、思考停止状態に陥っていないか?
●本当に相手の立場に立って物事を考えられているか?
●自分独自の価値体系を確立できているか?
●逆に自分の価値観に縛られ過ぎていないか?
●曖昧なものを受け入れていくことが出来ているか?
●言語化に関して、内省することはできているか?
これらは特にマネージャーとして働くうえで、重要なことです。
ただ、いきなりこういった質問に答えるのもちょっと負担ですよね。
そこでまずオススメしたいのは、「ミイダスの無料コンピテンシー診断」です。
かなり「回答しやすい」設計になっていて、所要時間は10分程度です。
ミイダスのコンピテンシー診断
自己診断を行うことで、自分で気づいていない自分の特性が分かるようになります。
私の診断結果は以下のようなものでした。
自己診断を行うことは、ある意味「自分の弱さ」とも向き合うことになります。
私の場合、明らかに「他人の考えを重視しない」ということがネックです。
しかしそれは、逆に言えば「意識して、相手のことを尊重する」ことをすれば、大きく改善すると気づけました。
このように、弱さを知ることは多少怖いですが、それを超えたメリットが自己診断にはあります。
●自分の強さについて再認識できるので、今後意識して活用できる。
●自分の弱さについて認識できるので、今後修正することで強くなれる
●自分の強さ・弱さを理解していると、自信をもって部下に対応できる。
また、このコンピテンシー診断は、今転職を考えていなくても利用することができます。
具体的な使用例について知りたい方は、ぜひ以下リンクからご覧ください。
まずは、もっともっと自分に向き合ってみましょう!